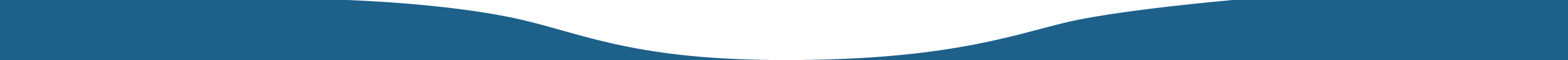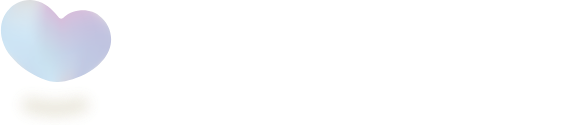目次
HSPとは

HSP(Highly Sensitive Person)とは、病名や診断名ではなく、個々の人が持つ気質を指す言葉です。HSPの人は、視覚や聴覚などの感覚が敏感であり、環境の変化や社会的な刺激に過敏に反応する傾向があります。
HSPの人は、日常的な些細なストレスから、精神疾患になりやすい傾向があります。過剰な落ち込みや、精神的ストレスを自覚し始めた場合には、周囲による適切なサポートや理解が必要となります。
HSPの原因
HSPの原因として「遺伝的要因」「脳機能の働き」「環境要因」「自律神経の乱れ」などが挙げられます。
原因1. 遺伝的要因

HSPの特性は遺伝的に決定される部分が大きいとされています。親から受け継いだ神経系の敏感さが、HSPの特徴を形成する一因となっています。
原因2. 脳機能の働き

HSPは、感覚情報を処理する脳の部分が他の人よりも活発に働くことが確認されています。このため、環境や他人の感情を敏感に感じ取りやすくなります。
原因3. 環境要因

過度に保護されたり、逆に過度なストレスを受けたりした経験など、さまざまな環境要因によって、HSPになる恐れがあります。また、HSPは、何か一つの大きなストレスではなく複数が組み合わさることで、発症する原因となることも。
このように、幼少期の発育環境や日常的に潜む些細なストレスも、HSPを発症する主な原因となりうるのです。
原因4. 自律神経の乱れ

HSPの気質を持つ人は、「感覚過敏」「共感力の高さ」「心理的ストレス」「自己肯定感の低さ」などから、自律神経へのストレスを与えやすく乱れを引き起こしやすい傾向があります。自律神経が乱れると、気質を悪化させるほか、精神疾患の発症のきっかけになることもあるのです。
HSPとの向き合い方
HSPは、生まれつきの気質であり、治療や完治が難しいとされています。HSPは病気ではなく、感受性が強いことが特徴の一部です。だからこそ、この特性を理解し、どのように対応するかが重要です。HSPの人は、他人の感情や周囲の環境の変化に敏感で、ストレスや疲労を感じやすい傾向があります。
まず、自分の限界を知り、無理をしないことが大切です。HSPの特性によって疲労を感じる場合は、定期的に休息を取り、静かに過ごす時間を意識して確保することで、心身のバランスを保つことができます。また、刺激の多い場所では滞在時間を短くするなど、自分に合った環境を整えることも大切です。
他人の期待に合わせるのではなく、自分のペースで行動し、自分自身を大切にすることが、HSPの人にとって良い向き合い方です。さらに、家族や友人に自分の特性を理解してもらい、サポートを頼ることで、無理をせず安心して生活を送ることができるでしょう。HSPは治療が必要なものではありませんが、特性を受け入れ、適切な自己ケアを行うことで、健やかに過ごすことが可能です。
HSPでよくある質問
-
HSPの人へ言ってはいけない言葉や注意すべきことはありますか
-
HSPの人に対しては、「神経質すぎる」といった否定的な表現や、「普通はそこまで気にしないでしょう」といった感受性を否定するような発言は避けるべきです。
HSPの人は他人を優先しすぎてしまい、自分の気持ちを後回しにする傾向があるため、その人の気持ちを尊重し、引き出すように配慮することが重要です。
-
HSPは治りますか?
-
HSPは病気ではなく、生まれつき持っている気質ですので、治療する必要はありません。
ただし、HSPによって引き起こされる症状は治療で改善することが可能です。
症状によっては専門医が治療計画を立ててくれる場合もありますので、自己判断せずに専門医に相談することが重要です。
治療法について詳しく知りたい方は、ご予約の上、来院時にご相談ください。
-
HSPは遺伝しますか?
-
HSPの気質は、遺伝的要因と環境的要因の両方が関与しているとされています。
平均年齢17歳の約2,500人以上の双子を対象とした研究では、感受性や神経質度合い、内向性に遺伝的な要素があることが示されています。